|
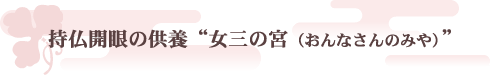
 夏の蓮花の盛りの頃、源氏の年の離れた正妻“女三の宮”の出家を祝って、持仏開眼の会が盛大におこなわれることとなりました。 夏の蓮花の盛りの頃、源氏の年の離れた正妻“女三の宮”の出家を祝って、持仏開眼の会が盛大におこなわれることとなりました。
正妻とはいえ、あまりに幼い“女三宮”に感心を寄せていなかった源氏の君ですが、彼女の出家の決意を聞いたときにみせた狼狽と執着は、読むものを驚かせるでしょう。失うと思うと急に惜しく感じてしまう、人間のサガというものが良くあらわされているなと感じます。
源氏が彼女のために用意した仏具や持経は、目を見張るほど美しいものばかりで、場面では馥郁と薫物の香りが漂います。
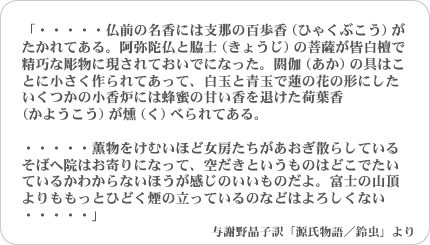
この、おごそかな仏前に備えられた「百歩香」とは、唐より伝わった薫衣香の優れた処方の名称で、百歩先までその香りが感じられるほどの名香です。 さらに白檀で作られた神聖な仏像が飾られ、貴重な玉を蓮の花形に彫刻した可愛らしい香炉には、夏の香り”荷葉”の練り香が、蜜を控えて涼しげにその香りをたなびかせていました。
また、高価な薫物を煙いほどにたなびかせている様を見た源氏の君は、室内に焚きしめる空薫きは、どこで焚かれているのだろうかと思うほどに控えめなのが良いのですよ。富士のお山よりも煙がたなびいては、風情がありません。と女房たちをいさめるのでした。
|


