「若紫の巻」より・・・
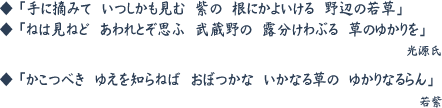
「源氏物語・若紫の巻」には、源氏にもっとも愛されたといわれる“紫の上” の幼少時代のお話が綴られています。
父である帝の后“藤壺”との許されない恋に苦しむ光源氏は、あるとき垣根越しに可愛らしい十歳ばかりの少女をみつけ、目を奪われます。
すでに母を亡くし祖母にあたる尼君に育てられていたこの姫君は、“藤壺”の姪にあたるため、面差しが恋しい彼女に大変似ていたのでした。

少女を自分の手元に引き取りたいと思う源氏は、尼君が亡くなるや、さらうようにして自邸へと連れ出してしまいます。
急なことにどのようにして良いものか、寂しそうにしている姫君の機嫌をとり、そばにいる源氏は、

 と、歌を投げかけます。
と、歌を投げかけます。
武蔵野の地は、その昔、紫草の自生する名所でした。
この「ねは見ねど・・・」は、紫草の根をさし藤壺と縁のつながった方という意味と、いずれ抱くことになる少女に対し「寝はみねど・・・」という暗示が含まれています。
あどけない様子の姫君は、源氏に返事を促され、
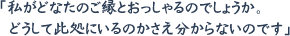
と、不安な様子で答えるのでした。
やがて理想の女性へと育て上げていく“紫の上”との出会いの場面を描いたこの巻を、作者である紫式部が「若紫」と名付けたのも、若草萌える紫草のみずみずしさを、幼い姫君の清らかさと重ね合わせてのことでしょう。
 「源氏物語」は、当初「紫のものがたり」といわれたように、紫にゆかりの深い名前の女性が重要な役割をになって登場します。
「源氏物語」は、当初「紫のものがたり」といわれたように、紫にゆかりの深い名前の女性が重要な役割をになって登場します。
“藤壺の君”とは、桜の散りゆく春の終わり頃より、淡い紫色の房を優雅にたらして咲く藤のある住まいにおられる女性を意味しています。
源氏の父君である“桐壺の帝”の寵愛を一身に受けていた彼女ですが、義理の息子である光源氏に慕われ、とうとう不義の子を宿してしまいます。
 その後、彼女はその罪の恐ろしさから彼を拒み続け、ついには出家の道を選ぶのでした。
その後、彼女はその罪の恐ろしさから彼を拒み続け、ついには出家の道を選ぶのでした。
幼いころに生母を亡くした彼にとって、面差しが良く似ているといわれる藤壺の君は、憧れてやまぬ初恋の相手であり、手の届かない永遠の女性として物語の中、源氏の心をとらえ続けていくことになるのです。
高貴であり敬意を表すにふさわしい色として“紫”を愛した平安時代は、次第に「濃き」といえば「濃紫」を、「薄き」といえば「薄紫」を暗黙のうちに意味するようになっていきます。


