|
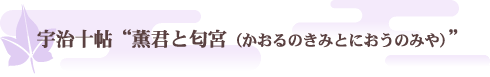


薫君は、光源氏の年の離れた正妻“女三宮”と若き“柏木”との間に生まれた不義の子で、源氏は、この事実を知りつつも表向きは実子として彼に接します。
このように、罪を背負い生まれてきた薫君は、うすうす自らの出生の秘密を知るにつれ、どこか厭世的で憂いを秘めた青年に成長していきました。
彼の性格は、光源氏の”陰の部分”を表しているといわれます。
また彼は、生まれながらにして”なんともいえず不思議な芳香”を身体に備えていました。
その香りの素晴らしさは、文中でこのように表現されています。
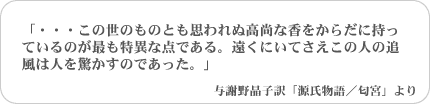
平安時代、身につける衣に香りを焚きしめることは、高貴な男女の身だしなみとして欠かせないものでした。
高価で貴重な渡来の香料を用いて作られる薫香は、その方の身分から人格・教養までを一瞬にして表現することでもあるため、各自が熱心に創意工夫して香りの調合に努めたのです。
薫君には、いかに優れた処方の薫物にも勝る、不思議な芳香が身体にそなわっていたのでしょう。
 中国には、身体に芳香を持つ美女のお話が残されていますが、その代表ともいえるのが“香妃(こうひ)”や“楊貴妃(ようきひ)”でしょう。 中国には、身体に芳香を持つ美女のお話が残されていますが、その代表ともいえるのが“香妃(こうひ)”や“楊貴妃(ようきひ)”でしょう。
唐の玄宗皇帝(げんそうこうてい)に溺愛された楊貴妃は、湯浴みをした水にまで良い香りがうつったといわれていますが、当時異民族の強い体臭は珍重される傾向があったようです。イラン系の血を引く美女だったといわれる彼女には、独特のエキゾチックな体臭が具わっていたのかもしれません。
|


