日々の暮らしの大きな節目となる「お正月」、日本人はこの日を一年の初めとし、様々な「しつらい」をほどこしてきました。
祝い花としての「花を飾る」という行為もそのひとつでしょう。
年月を木肌に刻み、大地にシカと根をすえた常磐木の松、わずか三日でその身を天へと伸ばす竹、リンとした寒気のなか清らかな香りとともに蕾をほころばせる梅の花、そして難を転ずるいわれの南天や早春花・水仙など・・・。
新年にふさわしい植物を選んで飾られるこの行為には、日本人が育ててきた神、そして自然に対する精神的な思いが投影されています。
今回は、祖先の花に対する扱いの歴史をとおして「ものいわぬ花の静かな語り事」に耳をかたむけてみましょう。

 依代(よりしろ)・・・神霊が天より降臨し宿るもの
依代(よりしろ)・・・神霊が天より降臨し宿るもの
豊かな自然は、私たちに大きな恵みをもたらしてくれます。が、時として激しく荒れ狂い、恐ろしい厄災を引き起こすことも少なくありません。
故に古代人が何か事あるたびにその力の偉大さを感じ、そこに神の姿を見出したのも理解できることでしょう。
本来、神とはその姿をもたず又、ひと所に定着するものではないと考えられてきました。

天より降臨した神霊は、様々な物体である依代を媒体として宿るのです。
鎮座する巨岩、うっそうとした山、樹齢を重ねた樹木など人々は霊気の感じられるその場所で祈りを捧げ、神に対する畏怖の念をあらわしたのです。

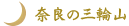
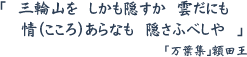
都が飛鳥から近江へと遷ることとなり、この地で生を受けた額田王(ぬかたのおおきみ)にとって、何かにつけ手を合わせ心のよりどころとしていた三輪山とのお別れは悲しいものでした。
だのに雲は、いじわるをするかのように三輪山に覆いかぶさってしまいます。どうぞ心があるならば、あの御山を隠さないでおくれ・・・、と歌に託して語りかけるのでした。
「古事記」や「日本書紀」にも登場する奈良県桜井市の“三輪山”は、古代より神聖な神の住む山としてあがめられてきました。
草一本、石ころひとつ取ってはいけないとされる山中には、神の依代である「磐座(いわくら)」が祀られ、多数の勾玉や神器が発見されています。
奈良県よりJR桜井線に乗り「天理駅」を過ぎると、大和盆地の静かな景色の中、大きな鳥居の先にたたずむ穏やかな円錐形の神山“三輪山”が見えてきます。その先の「三輪駅」で下車し、徒歩で5分もすると、三輪山を御神体とする『大神神社(おおみわじんじゃ)』に到着します。
じつは、日本最古の神社といわれるこの大神神社には、本殿がありません。
鳥居をくぐって参道を抜けた先にある拝殿の奥には、木々に覆われた三輪山が鎮座しており、その御山にむかって手を合わせるという、原初の神祭りの形式を今に伝える神社なのです。
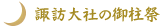
 「天下の奇祭」として有名な長野県・諏訪大社の「御柱祭(おんばしらさい)」は、トラとサルの年七年ごとに行われます。
「天下の奇祭」として有名な長野県・諏訪大社の「御柱祭(おんばしらさい)」は、トラとサルの年七年ごとに行われます。
八ヶ岳山中から神の宿るというモミの巨木を伐り出し、人の力で運び出して拝殿の四隅にたてるという豪壮なお祭りです。
祖先から脈々と伝えられてきた神聖なるこの儀式にあたって、モミの木から発する樹木の香気は、あたり一面を崇高な場へと変化させていくことでしょう。川越しや坂落としなど、命をもいとわない緊張の中、気持ちを高ぶらせていく人々の表情には、恐れることのない神への畏敬の念が感じらます。
仏教の教えもまだ渡来しておらず、大地の営みと共に生活していた古代の日本人にとって、神とは森羅万象そのものでした。
神の魂は自然の中に宿るとされ、生命力あふれる常磐木から、風化し死のイメージのつきまとう曝れ木(しゃれぼく)にまで、その霊気を感じとったのです。


