 “千利休”が“侘び”の世界である茶の湯に取り入れたのは、「投げ入れ」という実に簡素な花の姿でした。
“千利休”が“侘び”の世界である茶の湯に取り入れたのは、「投げ入れ」という実に簡素な花の姿でした。
投げ入れの花は、身分を取り去ることから始まる「侘茶」の世界において、もっともふさわしいものであると同時に、“美”というものの定義に新しい価値観を提示することになります。
千利休(1522~1591)・・・『一点の花を確立』
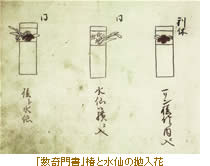 茶室という小さな空間は、自らの内面と向き合う場でもありました。
茶室という小さな空間は、自らの内面と向き合う場でもありました。
にじり口から身を低くして席入りし、スッと視線を上げた先に飛び込んでくる一輪の椿。
人はその瞬間、張り詰めた緊張感と装飾を超えた“真の美”を発見したことでしょう。
一輪の花のみですべてのことを表現しきったといえる、利休の代表的「投げ入れ」の形です。
さらに、千利休の花にまつわる逸話を紹介しておきましょう。
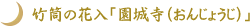
 草花の運搬のために用いられていた竹筒を、茶席の花入として応用した のは、利休の師である紹鴎(じょうおう)でした。
草花の運搬のために用いられていた竹筒を、茶席の花入として応用した のは、利休の師である紹鴎(じょうおう)でした。
1590年、秀吉の小田原出陣に同行した利休は、自ら韮山の竹を切り、その頂に輪を残して窓を開けた花入を作ります。 正面にある雪われの二筋を園城寺の割れ鐘にみたて名づけられたこの花入は、単なる竹筒を完成度の高い造形作品として昇華させることとなり、後世の竹花入れの基本的スタイルとなりました。
現在、上野の国立博物館に収蔵されているこの花入れを見ると、想像よりもガッシリと太く、利休が斧で切り出す際の力強さを感じることができるでしょう。

ある時、天下人秀吉は、大きな金の鉢と一枝の紅梅を利休に差出し「花仕 れ」と命じます。果たして居士はどの様な花を生けたのでしょうか。
彼は、大きな鉢に水をたたえた後、清らかに咲いた梅の花を水中へと掻き 落とすという独創的な発想で花を生け、秀吉を驚嘆させるのでした。

 この細く長い鶴首形の器は、底に波寿文の高台がつき、格調たかい胡銅の 花入として伝えられています。
この細く長い鶴首形の器は、底に波寿文の高台がつき、格調たかい胡銅の 花入として伝えられています。
利休は、この器を床に置き、なみなみと水のみを湛え、究極とも言える茶席の花とするのでした。
このように器に水だけをなみなみと張ったという記録が、利休の茶会記に6回記されてます。 生命の源である水の命をめでることこそ、彼の打ちたてた「投げ入れ」の美学を象徴しているのでしょう。
通俗的な観念にとらわれず、次から次へと常識を打破していった千利休。
しかしながら、彼には、切腹という最期が待ち受けていたのです。
利休のなしえた新しい価値観の確立には、権力に対して信念を曲げない気骨の精神が感じられ、そうした厳しさが、茶の湯や花の美学に反映されて私たちをとりこにするのでしょう。
「花は野にあるように・・・」そう茶席の花を説いた利休ですが、自然を人間の手で表現することほど難しいことはありません。
見る人にあの自然の清らかさや抱擁力を思い起こさせ、心に入り込む花を生けるには、定まった生き方の美学なくしては生まれないことなのでしょう。
「投げ入れ」とは、見向きもされない野菜の花にすぎなかった菜の花を、茶席の花に用いた利休のように、“草”に見える花の中に“真”が隠れていることを伝える花なのです・・・。


