
『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。

「十一月の平薬(ひらくす)」
『懸物圖鏡(かけものずかがみ)』西村知備(にしむらともなり)著
「五穀豊穣の稲穂飾り」「鶴若松紋時代蒔絵三宝」
新穀・榊・奉書紙・麻ひも十一月二十三日に執り行われる「新嘗祭(にいなめさい)」は、
その年に収穫された穀物に感謝を込めて神様にお供えをし、
天皇自らも新穀をはじめて口にされる宮中行事です。
農耕民族である日本の稲作は縄文時代からはじまりました。
お米は精霊が宿る神聖な穀物として、
日本人の精神に特別な思いを持って刻み込まれていくことになります。
今年収穫された稲穂と榊葉をもちいて「五穀豊穣の稲穂飾り」を製作しましょう。
重たげに穂を垂れる稲を一本一本清めていくと、
どこか懐かしいような稲藁の匂いにつつまれ、
幼い日に父の田舎で遊んだお米の収穫の風景がよみがえってきます。

「青森県の生産者よりとどいた新穀」
青さの残る稲穂から豊穣の香りが漂いますパンやスパゲッティなどが食卓に並ぶようになり、
毎日食することのなくなったお米ですが、
旅先の車中からながめる田んぼの風景はいつも私の心を和ませてくれます。
爽やかな五月の風に揺れる水面の早苗、天に向かって
伸びゆく初夏の若草、
重たげに穂を垂れ実りにさえずる雀たち、
そして収穫の後の静まり返った田の風景。
季節とともに変わりゆくその風景に触れるたび、
自然の摂理がかくも正しく巡回しているように感じ心は安堵するのでしょう。
日本の原風景といえる稲田は、これからどうなっていくのでしょうか。
できることならば未来の子供たちとも、この感慨を共有したいものと願います・・・。

「寒椿の香袋」
(材料)絹裂・打紐・綿・白檀・香料薔薇・丁子・桂皮・龍脳じつは椿は香りをもたないお花です。椿によく似たサザンカの花には芳香があるのですが、椿にはないのです。もしも椿が香りを放つとしたら、古代から愛されてきた神秘的な芳香がふさわしいのではないでしょうか。
今回は東洋で愛され神へと捧げられてきた白檀と、西洋で愛され人々を魅了してきた薔薇をあわせて椿香の香りといたしましょう。薔薇と白檀の相性は大変よく、古代薔薇の麗しい芳香は東洋の神秘の香木と巡りあったことで落ち着きが加わり、春の到来を呼び込む花にふさわしい存在感をかもしだすことでしょう。
~つらつら椿 つらつらに~
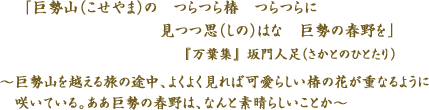
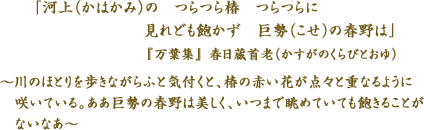
万葉集におさめられているこれらの歌は、
~つらつら椿 つらつらに~ という軽やかなリズムをともなって
春の到来を待ち望む思いを伝えてくることでしょう。
大和の時代に人々が行き通った巨勢路とは、
当時都であった奈良から和歌山県吉野へと続く道でした。
奈良の神山・三輪山の麓に位置する町・海石榴(つばいち)は、
日本で最初にできた市といわれ旅の交差点として大いに賑わいました。
またこのあたりは椿の自生地としても有名で、
初冬から春にかけて咲き誇る藪椿の赤い花は、
霊所といわれる熊野地方へと近づくにつれ山を覆うような大木となって野性味を増していきます。
巨木となった椿の森をぬけるとき、
人々はこの植物から発せられる力強いエネルギーと神秘的な霊気を感じとったことでしょう。

正倉院宝物「椿杖」
平安時代、宮中では正月初めの卯の日に年中の邪気をはらうため、杖で大地をたたく儀式が行われました。奈良の正倉院にはこの神聖な儀式に用いられた椿の木の杖が伝わっています。民俗学者である折口信夫先生は“椿は春の木”と語り
山の民が里におりて春を言触れる際に持ち歩いた木として紹介しています。
また日本海側の海岸線沿いにある椿の群生をみて、
これらは野生ではなく春を告げる神聖な椿を大切に思った人々が、
南から北へと移動し生きる範囲を広げていく中で種を携え
おのずから植えていったのだろうと推測しています。
太古から続く日本の原風景には、春を謳歌する山桜と共に、
冬の厳しい寒さにも艶々とした常緑の葉をもって鮮やかな真紅の花を咲かせる
藪椿の原生林が存在していたのです。
~安達瞳子さんと『百椿図』~
 「百椿図絵巻」部分
「百椿図絵巻」部分平成十八年三月、椿をこよなく愛した花道家“安達瞳子”さんが息をひきとられました。
凛とした着物姿の美しいたたずまいと、意志の強さをあらわす黒く大きな瞳は、
多くの人々の印象に深く刻まれていることでしょう。
世田谷の自宅に植えられた一万五千本もの椿の木が象徴するように、
この花と彼女との深い関わりは「安達式挿花家元」だったお父様と
ある巻物との出会いによって始まります・・・。
戦後間もない昭和二十二年、
通りすがりの銀座の骨董店に飾られてあった絵巻物に目を奪われた瞳子さんの父親は、
迷わず店主に詰め寄り、すでに外国の方の手付きが入っていたこの巻物を手に入れます。
じつはこれこそ江戸時代に松平忠国が企画編成して描かせ、
長く所在不明とされていた『百椿図(ひゃくちんず)絵巻』の古写本だったのです。
巻物を紐解くと、中から太鼓や扇子などのあしらいとともに描かれた数々の椿の花があらわれ、
雅で華麗な美しさをはなっているのでした。
 「百椿図絵巻」部分
「百椿図絵巻」部分『百椿図絵巻』の由来
徳川家康が江戸幕府を構えたとき、
その祝いの品として気品ある“白玉椿”が献上されました。
“八千代の栄え” “長寿”というこの椿につけられた花言葉に、
徳川家の繁栄の願いが込められていたのでしょう。
白玉椿はその“白玉”という名前にもあるように、
まん丸で可愛らしい蕾をつける早咲きの品種で、
茶の湯の正月に当たる
十一月の“開炉”にふさわしい花として飾られることが多く現在でも大変に愛されています。
室町時代より武家の間で流行していった茶の湯は、
花を活ける文化に「投げ入れ」という新しいスタイルを生み出しましたが、
千利休により確立されつつある侘茶の美意識にふさわしい茶花として、
枯淡な椿は好まれるようになっていきました。
寺や公家・大名の庭園に様々な植物が植えられるなか、
庭木としての椿はさらに人気がたかまり、
豊臣秀吉の築城した伏見城にはじつのたくさんの椿が植えられ
「椿の城」とよばれるようになります。
とくに二代将軍・徳川秀忠の椿好きは有名で、
日本各地の大名に椿を献上させ江戸城内の花畠に椿の大庭園を築くのでした。
やがて椿愛好は文化人のステイサスとなり、
名花や珍花の収集のほか交配に情熱を注いで生まれた園芸種が次々に誕生していきました。
この椿ブームは寛永の平和な時代を反映して庶民にまで浸透し、
多彩なる江戸椿文化が花開くことになります。
 「百椿図絵巻」江戸時代 根津美術館蔵
「百椿図絵巻」江戸時代 根津美術館蔵そうした熱狂の中、徳川家康の甥で丹波篠山の城主だった松平忠国は、
狩野派の絵師・山楽に様々な椿の画を描くことを依頼します。
仕上がってきた椿図はじつに繊細で美しく忠国をおおいに満足させるものでした。
そこで彼はこの椿の絵に当時の名だたる名士による
和歌・俳諧・漢詩を添えることを思いつきます。
総勢四十九名の文化人によって添えられた五十二首もの画賛は、
椿二図または三図を一つとした構成でしあげられ、
十三枚継ぎ全二巻の「百椿図絵巻」として完成するのでした。
近年この原本とされる絵巻物が、さる旧家から根津美術館に寄贈されていたことが判明し、
平成十五年三月・日本橋の三越で初めて全巻公開される運びとなりました。
『椿物語展』と銘打ったこの展覧会は、
椿をこよなく愛し椿に育てられたと語る安達瞳子さんの長年の想いを綴る物語として構成され、
彼女の椿を用いた「花芸」の作品と共に華やかに公開されたのです。


花芸安達流家元の安達瞳子先生
花芸作品「つらつら椿」青竹創作花器に黒松・椿・菜花椿の花を思うとき、私の心にいつも浮かび上がるのは安達瞳子先生の面影でした。
先生にお会いできたのは、平成十二年帝国ホテルでの授賞式でした。
世界文化社主催の家庭画報大賞に応募した私は幸運にも帝国ホテル賞に入選し、
その表彰式で審査員のひとりになられていた安達先生にお会いできたのです。
いつものように清楚な白い着物と帯の装い、
そして涼しげな水色の帯締め姿の先生は、
静かな微笑みの中にも太古から受け継がれてきたかのような
日本女性のシンの強さを秘めてたたずんでおられました。
授賞式後のパーティでお写真のお願いをすると気持ち良く受けてくださり
「あなたの作品好きですよ」と声をかけてくださったことが何よりも嬉しい思い出です。
安達流の後継者として育てられたものの父親との確執から家出、
さらに絶縁されるという激しい生き方をされた先生は、
平成十八年三月十日、椿の花がポトリと散るように七十歳の生涯を閉じられたのでした。
真紅の花びらに黄色の蕊を抱いた藪椿の妖艶な美しさと、
大地に根をはり巨木に成長するたくましさを先生の面影にかさね、
懸命に生きられた安達瞳子先生のご冥福を心よりお祈り致します。

