
『香り花房・かおりはなふさ』では、日本の香りと室礼文化を研究しています。
 古銅獅子香炉から立ち昇る香煙
古銅獅子香炉から立ち昇る香煙源氏物語「梅枝の巻」には、
源氏の娘である明石の姫君が東宮に入内することとなり、
持参させるための薫物の調合を四人の女性たちに競わせるという話が綴られています。
平安時代の香りの主流は「練り香」と呼ばれるものでした。
渡来ものの様々な香料を粉末にして調合する練り香は、
微妙な匙加減で香りに変化が生じます。
平安貴族にとって優れた薫物をくゆらすことは、香りを聞いたその一瞬で
その方の身分から人格・教養までを表現してしまうほどに重要なことだったため、
人々は優れた練り香の調合にいそしんでいたのです。
この薫物合わせに参加した四人の女性たちは、
それぞれの人となりを表すかのような香を調合し源氏の君を喜ばせます。
女同士の嫉妬に巻き込まれるのを避け最後まで源氏の愛を拒み続けた“朝顔斎院は、
もっとも格の高い「黒方(くろほう)」をじつに趣ある伝統的な香りに仕上げました。
フォーマルで正統といえるその芳香は、
高貴な生まれに育った芯の強い朝顔斎院にふさわしいといえるかもしれません。
“紫の上”の調合した「梅花(ばいか)」は、
梅の花になぞられた華やかな仕上がりとなりました。
作者である紫式部は源氏の寵愛を誰よりも受けたといわれる紫の上に、
当時もっともモダンで注目に値する梅の香をつくらせ
美しいこの花にふさわしい女性であることをしめしたのでしょう。

「紅梅」
清少納言は「枕草子」に「・・・梅の花はうす色でも濃い花でも、とにかく紅い花・・・」 と記しています。 季節を色に染め上げ衣として身にまとっていた宮廷の女性たちにとって、少し青味がかったやさしい紅梅色は、このうえなく優雅な早春の色としてもっとも愛されたのでしょう。すべてにおいて控えめに源氏をジッと待ち優しく迎える“花散里の御方”は、
夏のしめやかなる香り「荷葉(かよう)」を調合しました。
荷葉とは蓮の葉のことで夏の厳しい暑さの中、涼やかさを印象づける芳香です。
その調合にある“安息香”の処方によって
スッとした清涼感漂うしめやかな香りに仕上がるのです。
 微粉末の様々な香料を練り合わせつくる練り香
微粉末の様々な香料を練り合わせつくる練り香そして四人目の女性“明石の御方”は、いったいどのような香を作られたのでしょうか?
じつは姫君の実母である彼女は、源氏が須磨に隠遁している時に知り合った女性で
生まれた女の子とともに京へと呼び寄せられます。
源氏は娘を高い地位の方へ嫁がせようと考えましたが、
それには母親である明石の御方よりも高貴な後立が必要なため
姫君の養育を紫の上に託することにするのでした。
愛するわが子を手放さなければならない明石の御方、
子を欲しいと思うものの授からず他の女性との子を育てることになった紫の上。
双方にとり胸を痛める現実でしたが、姫君の愛らしいまなざしに紫の上の嫉妬もおさまり
やがて母となる喜びを感じるのでした。
彼女は練り香の代表とされる“六種(むくさ)の薫物”を調合することを控え、
衣に焚きしめる「薫衣香(くのえこう)」をつくります。
その行為には他の姫君たちよりも劣っている自分の身分を考え、
競い合うことを避けた彼女の賢さと奥ゆかしさが感じ取れるでしょう。

「六種の薫物」鳩居堂製
平安時代に記された「薫集類抄(くんしゅうるいしょう)」という書物には、練り香の詳細な配合が記されており、当時の香りの詳細を知ることができます。源氏の屋敷で行われた風流な薫物合わせの結果は、
「どれも優劣しかねるほどに優れたものである」
との蛍宮の判定がくだされ和やかなままに終わりをむかえます。
それぞれの女性たちの印象を忍ばせる薫物合わせとなりました。
こうして姫君が入内した後、紫の上はこれ以後の後見人に明石の御方を立て、
ふたたび実の母子が共に暮らす時が訪れるのです。

「源氏物語画帖/梅枝」徳川美術館蔵
薫物合わせをする光源氏と兵部卿の宮。梅の枝をさした練り香「梅花」と松の枝をさした練り香「黒方」の壺が描かれる。薫物合わせも終わり、月の出とともにお酒が運ばれてきました。
寝殿の中は様々な薫香の香りに満ち満ち、
雨上がりの柔らかい風にのって庭に咲く紅梅の清らかな芳香がしとやかに流れ込み、
何ともいいようもないほど雅な夕暮れとなりました。
やがて夜明けに帰るため席を立った蛍宮に
源氏は直衣一揃いと香の壺を二つ土産として宮の牛車へと届けさせます。
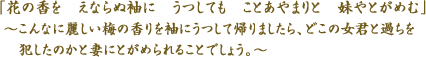
と、和歌にしたためた蛍宮に対し源氏の君も和歌をおくります。
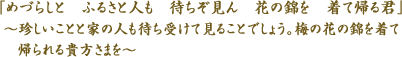
しかし実はこの時、蛍宮は長年連れ添った北の方を亡くされたあとで
帰っても迎えてくれる妻はいなかったのです。
その寂しい心情を覆い隠して歌にした宮に対し
源氏もまた彼の心に思いを馳せつつ和歌をおくったのでした。
ともに風雅を愛する男たちの知的な交流がみてとれるでしょう。
「源氏物語」は多くの登場人物とともにそれぞれの多様な人生模様が描かれていますが、
作者”紫式部“はそれらの場面を具体的な言葉で表現するだけでなく、
じつに効果的に香りをくゆらせ
より情感深く言わんとしていることを伝えているのです。

